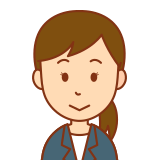
会社によって生理休暇があったり、慶弔休暇があったりするけど、企業が最低限絶対に定めないといけない有給休暇(=賃金が支払われる休暇)は何がある?
労働基準法に基づいて、企業が労働者に対して絶対に定めなければならない休暇の種類は以下の通りです。
- 有給休暇: 労働者が6か月間継続して勤務し、その間に80日以上出勤した場合、年間最低10日の有給休暇を付与する必要があります(労働基準法第39条)。付与日数は勤続年数に応じて増加します。
- 週休: 週に1日以上の休日を確保することが求められています(労働基準法第35条)。4週間のうちに4日以上の休日を設けることが必要とされています。
- 休憩: 労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与える必要があります(労働基準法第34条)。
これらの休暇は労働者の健康と労働環境の改善を目指したものであり、企業はこれらの休暇を遵守しなければなりません。
なお、祝日については祝日法によって定められていますが、祝日法は労働基準法とは異なり、私法的な性格を持つため、企業に対しては必ずしも強制力を持つわけではありません。しかし、労働契約や就業規則、労働協約などで祝日を休日とすることが定められている場合が一般的です。
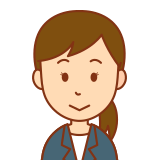
ということは、生理休暇や慶弔休暇などの休暇は、企業が定めていなくても法律違反にはならないんですか?
はい、その通りです。慶弔休暇や生理休暇などは企業が自主的に設けるものであり、これらを設けない企業があってもそれが直接的な法律違反になるわけではありません。
なお、いずれの休暇も企業が設ける場合は、就業規則で明確にその取扱いが定められ、労働者に周知されるべきです。また、企業がこれらの休暇を設けている場合、一方的にこれを取り消すなどすると、労働契約違反になる可能性があります。そのため、これらの休暇の取扱いについては、各企業の就業規則や労働協約を確認することが重要です。
なお、生理休暇については、生理痛により労働が困難な場合には、労働者安全衛生法に基づく傷病休暇の対象となる場合があります。
参考出典:
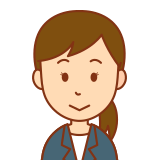
企業が自主的に設けている休暇の種類って何があるの?休暇の種類が多い会社に転職したい〜。
日本の企業における自主的な休暇の設定は様々で、企業の特性や業界により異なります。以下にいくつかの例を挙げてみます:
- 生理休暇: 女性社員が月経不調の際に取得できる休暇。企業によりますが
- 慶弔休暇: 社員やその親族の結婚、出産、死亡などの際に取得できる休暇。多くの企業で設けられています。
- リフレッシュ休暇: 社員の健康維持やモチベーション向上を目的とした長期休暇。
- ボランティア休暇: 社会貢献活動を行うための休暇。
- 育児休暇・介護休暇: 子どもの育児や家族の介護を行うための休暇。実際には、これらは労働基準法や育児・介護休業法によって保証されていますが、一部の企業では法律以上の取り組みを行っています。
- セーフティリーブ: メンタルヘルスを保護するために、社員が自分自身で自身の精神的な健康状態を考慮して休暇を取得することができます。
- 自己啓発休暇: 社員のスキルアップや資格取得のための休暇。
- 育休前休暇: 予定出産日前に取得できる休暇。産前産後休業の一部となりますが、特定の企業ではこの名前で独立した休暇として設定されていることがあります。
- 産後復帰休暇: 産後、育児と仕事の両立を支援するために設けられた休暇。
- パートナーシップ休暇: パートナーが出産や重病などで休む際に、その支援をするための休暇。
- ストレスケア休暇: 社員のストレス軽減を目的とした休暇。
- カレンダー休暇: 一年に一定の日数、自由に使える休暇。
- ドナー休暇: 社員が臓器または骨髄のドナーとなる場合の休暇。
- 看護休暇: 自分の子供が病気になったときに取得できる休暇。
上記はあくまで一部の例であり、具体的な内容や条件は各企業の就業規則や労働協約、社内ルールなどによります。
なお、企業により名称や制度が異なる可能性があり、各企業の就業規則や労働協約、社内ルールは通常、社員に対して開示されるものであるため、各種休暇の詳細については所属する企業の人事部門や上司に尋ねるのが最も確実です。
以下の関連記事もぜひ併せてご参照ください。



