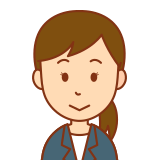
有給休暇についてどのくらいもらえるか計算したいので、いつもらえるかと日数、タイミング、もらえる条件が知りたいな。
有給休暇の付与日数と付与条件は、最低ラインが法律で定義されている
労働基準法(第39条)により、全労働者に対して有給休暇を付与することが義務付けられています。継続勤務期間が6か月以上で、その期間の勤務日数が80%以上の労働者に、年次有給休暇を付与しなければなりません。勤続年数により、付与される有給休暇日数は増えます。つまり、一定の基準は国が定めており、それ以下の日数を付与することは違法となります。
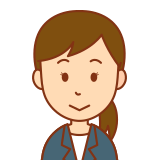
有給の仕組みとして、初年度は入社後すぐ付与されるわけじゃなくて、半年後にもらえるんだね。
付与のタイミングと回数についても最低ラインが法律で定義されている
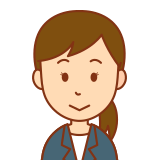
4月入社で週5日×8時間契約の私(正社員)はいつ、どれくらい増えるの?いつから使えるの?
正社員(週所定労働日数が5日)の場合
有給休暇がいつからもらえるか気になりますよね。有給の付与について具体的なタイミングと回数についても法律で定められています。具体的には、労働者がある企業に入社し、継続して6ヶ月以上勤務し、その期間において所定労働日の4分の3以上出勤した場合、その労働者に対して有給休暇が付与されます。これが最初の付与となります。この初回の有給休暇の日数は10日と定められています。
その後の有給休暇の付与は、最初の付与日から数えて毎年一回となり、その時点での労働者の勤続年数に応じて日数が増えていきます。具体的には以下の通りです。
入社して2回目(2年目)の付与タイミング/日数:入社後1年6ヶ月経過時点で11日
入社して3回目(3年目)の付与タイミング/日数:入社後2年6ヶ月の勤続で14日
入社して4回目(4年目)の付与タイミング/日数:入社後3年6ヶ月の勤続で16日
入社して5回目(5年目)の付与タイミング/日数:入社後4年6ヶ月の勤続で18日
入社して6回目(6年目)の付与タイミング/日数:入社後5年6ヶ月以上の勤続で20日
これらのルールは労働基準法第39条に明記されており、すべての労働者に適用されます。ただし、これらは最低限守るべき法律であるため、企業が自主的にそれ以上の有給休暇を付与することは可能です。つまり、企業の方針や労使協定によって、より多くの有給休暇が付与される場合もあります。
ここで具体的な例を挙げてみましょう。
例えば、ある企業に4月1日に入社した山田さんがいます。山田さんがこの企業で働き始めてから6ヶ月が経ち、その間に週5日以上働いた週が8割以上ある場合、山田さんは10月1日に有給休暇を得る資格を得ます。その資格を得た日から1年間で10日間の有給休暇が付与されるのですが、勤続6ヶ月経過時点の10月1日に付与して10月1日から使用できる会社が多いかと思います。
その後、山田さんがこの会社で続けて働き、入社から2年半(30ヶ月)が経過すると、有給休暇の日数が増えて、年間11日間取得することができます。さらに、山田さんが3年半(42ヶ月)以上働き続けると、有給休暇は年間14日間に増えます。山田さんの有給付与日が10月1日だとした場合、山田さんは毎年10月1日に有給休暇が付与されることになります(付与から2年経過しても使用しなかった有給があれば、毎年9月30日で消滅します)。
そして、山田さんが6年半(78ヶ月)以上続けて働くと、有給休暇は最大の20日間になります。以降、山田さんがどれだけ長く働いても、1年間の有給休暇の日数は20日間が上限となります。
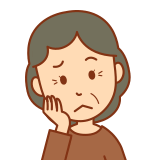
週3日×4時間=12時間契約の場合はどうなるの?いつ有給が増えるのかと増え方が知りたいわ?
パート・アルバイト(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満)の場合
以下の記事にて解説していますので参照ください。
有給休暇付与日数や条件は会社によって違うことがある
どの会社も上記の最低ラインを下回らないようにしているとは思いますが、会社によっては追加で付与するケースがあるなど、労働者の出勤日数や時間、契約形態(正社員、パートタイム、派遣など)によっても有給休暇の付与日数や取得の要件が異なることがありますので、具体的な規定については会社の就業規則や労働契約を参照して下さい。
以下の関連記事もぜひ併せてご参照ください。
出典:
- 労働基準法 第39条(有給休暇)
- 労働基準法施行令 第7条(年次有給休暇の日数)





