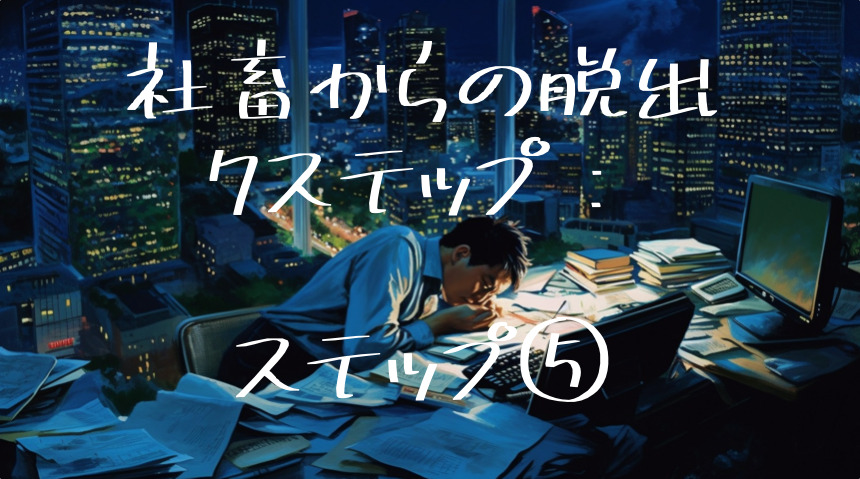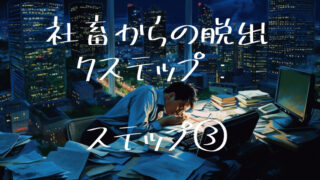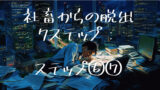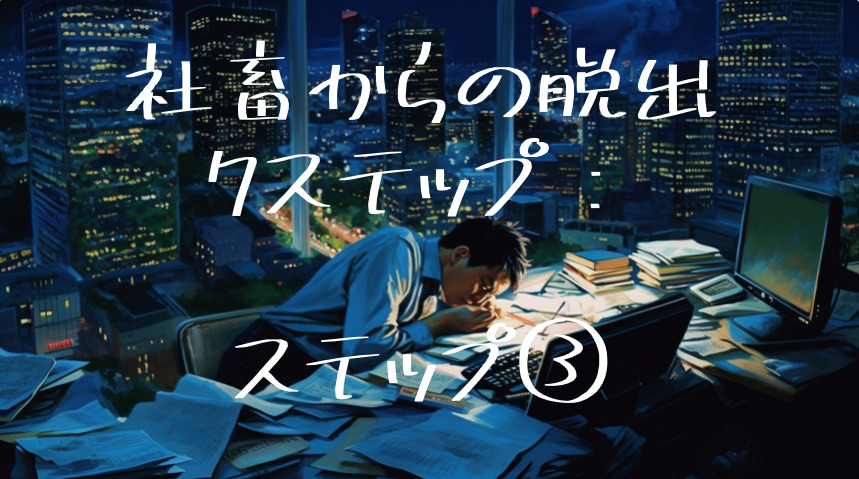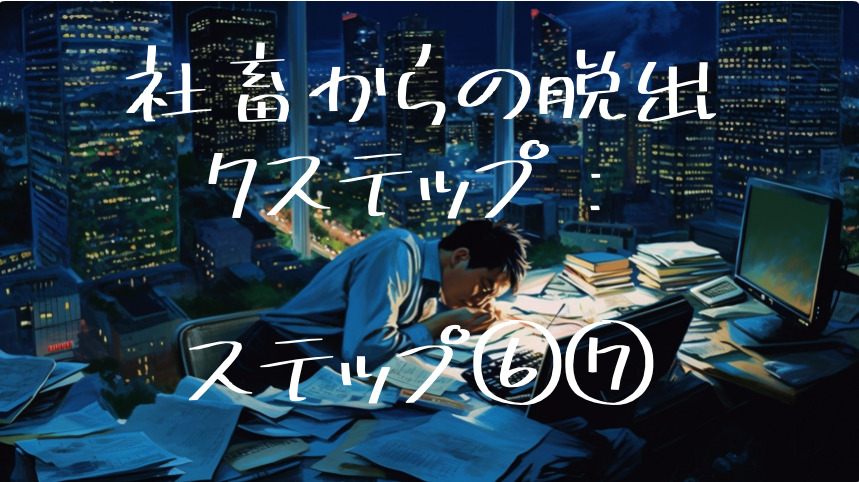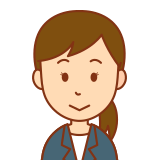
毎日朝が本当につらい、仕事に行くのがつらい、満員電車がつらい、職場の人間関係がつらい、給料が安くてつらい、残業が多くてつらい、もう辛いことしかない…
はじめに
「毎日毎日本当につらい…一体何でなの?」と感じているそこのあなた。この記事では、原因を深掘って深掘って、根本原因を突き止める実践的な方法を解説します。
まだ解決すべき課題が定まっていない方は、ぜひこちらの記事を参照いただき一番インパクトの大きい課題を明確にしてから読み進めてみて下さいね。
上記の関連記事で使用した具体例をこの記事でも引き続き使用していきます。
<具体例:QOL(生活の質)への影響が大きい課題TOP3>
| 課題 | 優先順位 | 評価基準 | 評価の理由 |
| 労働時間 | 1 | 長時間労働がすぐに健康に影響し、さらに他の生活領域にも悪影響を及ぼす。 | 長時間労働は身体と心に負担をかけ、すぐに健康問題を引き起こす可能性がある。また、労働時間が長いと自由時間が減り、家庭生活や趣味などの私生活への影響も大きい。 |
| 休暇日数・休暇制度 | 2 | 適切な休暇が取れないとストレスが溜まり、疲労回復やリフレッシュができない。 | 休暇が十分に取れないと、心身のリカバリータイムが確保できず、健康問題を引き起こす可能性がある。また、趣味や家庭生活など、仕事以外の活動への影響も大きい。 |
| 家庭や趣味などの私生活 | 3 | 私生活の時間が取れないとストレス発散やリラクゼーションができない。 | 自分の時間が確保できないと、ストレス発散の手段がなくなり、精神的な健康に影響を与える。しかし、労働時間や休暇と比べると、直接的な健康影響は少ない。 |
直接的な原因を考えよう
上記具体例で示しました、QOLへの影響度が大きい課題第1位の長時間労働について、まずは直接的な原因を考えてみましょう。私も社畜だった頃の一番の課題は長時間労働でした。では、なぜ私たちは長時間働いてしまうのでしょう? 原因として何が思い浮かびますか?
おそらく多くの方が思いつく一番明らかな直接的な原因は、「業務量が多い」ことではないでしょうか?ではなぜ業務量が多いのか、もう一段深く原因を追求していきましょう。
直接的な原因を深掘りしてみよう
「業務量が多いこと」というのはあくまで直接的な原因で、根本的な原因を突き止めるためにはもう少し深掘りする必要があります。つまり、「業務量が多いのはなぜか?」を考えるんです。
考えやすくするために、ここで一つ例え話をします。「レストランで提供される料理の量が多すぎる状況」を想像してみて下さい。あなたは上司と一緒にチームメンバー全員でレストランに来ています。上司が料理を注文して各々に皿を運んで食べさせています。あなたはすでに満腹で消化する時間が欲しいところなのですが、上司は次から次へと料理をあなたに提供してきます。では、あなたに提供される料理の量が過剰なのはなぜでしょうか?
・あなたは好き嫌いがなくめちゃくちゃ大食いだと思われている
・嫌いな料理に対して嫌いだと意思表示していない
・もう満腹で食べれないと意思表示していない
・上司から振る舞われた料理を完食しないと嫌われると思っている
・満腹宣言をしたら自分自身に負けた感じがしてしまう
などなど、考えられる原因はいろいろありますよね。
では話を戻しまして、業務量が多いのはなぜかを考えてみましょう。当然個々人の状況によって異なるとは思いますが、以下に一例を記載します。
従業員自身の問題
- スキルと業務量のミスマッチ:従業員が担当している業務に対する能力が不足している場合、一つの仕事を終えるのに通常以上の時間がかかり、結果として長時間労働につながる。
- 時間管理能力の欠如:時間を効率的に管理し、優先順位を設定する能力が不足していると、同じ業務量でも適切に処理できずに長時間労働になる。
- 意思表示の不足:自分の業務量が多すぎると感じていても、それを上司や同僚に対して適切に伝えられないと、更なる業務が追加されてしまう。
管理者の問題
- 業務量の認識不足:管理者が部下の業務量を適切に理解していないと、過剰な仕事を割り振る可能性がある。
- 人員配置の不適切さ:人員配置が適切でないと、一部の従業員に過剰な業務が集中し、長時間労働になる可能性がある。
- コミュニケーションの不足:従業員とのコミュニケーションが不足していると、業務量や仕事の進行状況、従業員の能力や状況を正確に把握することができない。
組織の問題
- 組織文化:長時間労働を美徳とする組織文化や、仕事が終わっても帰れないという無言の圧力が存在すると、従業員は自然と長時間労働するようになる。
- 業務プロセスの非効率性:業務プロセスが最適化されていないと、同じ結果を得るために余計な時間がかかることがある。
- リソースの不足:適切なツールやリソースが不足していると、業務効率が落ちて長時間労働につながる。
ここでは大きく①従業員自身の問題、②管理者の問題、③組織の問題というふうに3つに分けました。中には従業員自身ではどうしようもないことがありますので、「自分の意識や行動次第で変えられること」とそうではないことに分けることをおすすめします。
さらに深掘って根本原因を突き止める
「え、今深掘ったのにさらに深掘るの??」と思われた方が多いと思いますが、そうです、さらに深ぼって根本的な原因を突き止めましょう。つまり「意思表示の不足」を例にとるのであれば、「自分がなぜ意思表示をうまくできない/しないのか?」を深掘っていきます。
ここで、根本原因の特定に役立つフレームワークを3つ紹介します。あなたが使いやすいと思う方法で深掘りしてみて下さいね。
- 5W1H法:何(What)、誰が(Who)、いつ(When)、どこで(Where)、なぜ(Why)、どのように(How)といった基本的な疑問を用いて問題を深堀りします。
- フィッシュボーンダイアグラム(イシカワダイアグラム):問題の原因を人間、方法、材料、機械、測定、環境といったカテゴリーに分けて考え、それぞれの原因と結果の関係を視覚的に整理します。
- 5 Why(なぜなぜ分析):問題の直接的な原因からさらに「なぜ?」と問うことで、根本的な原因を探ります。5回「なぜ?」を繰り返すことで、原因と結果のチェーンをたどることができます。
では、具体例を使って一緒に深掘っていきましょう。ここでは「意思表示の不足」について、5 Why(なぜなぜ分析)を試みてみようと思います。
なぜなぜ分析とは何かというと、「問題が起こった原因に対して、なぜ?と質問を繰り返すことで、問題の根本原因を見つけ出す方法」のことです。
<具体例:「意思表示の不足」の根本原因を特定する>
1. なぜ自分の業務量が多すぎると感じても、それを上司や同僚に対して適切に伝えられないのだろう?
答え:自分の意見を適切に表現する自信がないから。
2. なぜ自分の意見を適切に表現する自信がないのだろう?
答え:自分でも自分の状況を正しく認識できていないから。ただ何となく業務量がキャパオーバーだと思っているだけで、実際自分は今どれだけの案件を抱えているか、完了させるにはあとどれくらいの時間が必要なのかを見積もれていないため、上司に伝える準備ができていないから。また、キャパオーバー宣言をした時に上司に受け入れられなかったらどうしようと、不安に思ってしまうため。
3. 上司に受け入れられなかったらどうしようと、不安に思ってしまうのはなぜだろう?
答え:自分の価値観や能力が否定されるのが怖いから。
4. なぜ自分の価値観や能力が否定されるのが怖いのだろう?
答え:それが自分の価値、あるいはチーム内での立場に影響を及ぼすと感じているから。
5. なぜそれが自分のプロフェッショナルとしての価値、あるいはチーム内での立場に影響を及ぼすと感じているのだろう?
答え:自分の意見や価値観が上司から否定されると、自分は能力が低い、仕事ができないやつだと思われて評価を下げられるのではないかと感じているから。
さて、これらの回答から見てみると、根本的な原因は「評価が下がることへの恐怖」なのかもしれませんね。それが「自己主張の不足」という現象につながっているようです。
それが本当に根本原因か考えよう
「え、それが根本原因じゃないの?」と思った方が多いと思います。根本原因の特定を誤るとこの後の対策立案や実行が見当違いのものになってしまう可能性があるので、慎重に、少し批判的に考えてみましょう。
「キャパシティ的に厳しいので業務量を調整して欲しい」という状況を上司に伝えたら、本当に評価が下がるんですかね??むしろ、キャパオーバーの状態で仕事を続けて、ミスが発生したり、報連相が疎かになったり、徹夜して寝坊して大事なMTをすっぽかすなんてことになった方が評価に響くと思いませんか?
私は長いこと管理者の立場で少なくない数の部下をみてきましたが、一般的に言っても、自身の状況を常に把握して、自身のパフォーマンスが最大限発揮されるように行動している人の方が生産性が高い傾向があるため能力が高く評価されると思います。
上記例の場合、根本原因は「上司に自分の状況を正しく伝えるための状況整理と理論武装の準備ができていない。準備することの重要性を認識していなかったので、準備する優先度を下げてしまっている。」と言うことになるかと思います。
「でもそんなこと言われたって自分一人では分からないよ!」と思った方もそうでない方も、根本原因を特定したと思ったらぜひ他者に聞いてもらって下さい。
課題の根本原因を掘り下げる作業は、自己反省や自己観察だけでは難しい場合があります。それは、自分自身の視点や経験だけでは限定的であり、また自己の視野には偏りがあるためです。
周りの人の助けを借りよう
そのため周りの人の助けを借りることが重要です。信頼できる同僚、上司、人事部門、産業医またはプロのカウンセラーなどに相談することで、自分自身では気づけなかった視点や解決策を見つけることができます。
例えば、以下のような手段が有効です。
他者との対話
上司や同僚、さらには職場以外の友人やパートナーと課題について話し合うことで新たな視点を得ることができます。彼らはあなたが見逃しているかもしれない視点を持っている可能性があります。
メンターやコーチの活用
メンターやコーチはあなたの視点を広げ、問題を別の角度から見るのに役立つ指導力を持っています。彼らは適切な質問を投げかけることであなた自身が解答を見つけるのを助けます。
フィードバックの活用
定期的なパフォーマンス評価や360度フィードバックなどの形で他者からの評価を得ることは、自己認識の一環として有用です。他人の視点は自己観察だけでは気付きにくい点を明らかにすることがあります。
専門家の意見
職場環境や労働問題についての専門家の意見を得ることも有益です。これには労働法の専門家や、職場の心理状況を理解するための産業心理学者などが含まれます。
以上のような多角的な視点を取り入れることで、より深く、かつ広範に自身の課題の根本原因を理解することが可能になります。そしてその理解が、より適切な改善策を導き出すための第一歩となります。
おわりに
ここまで原因分析の実践的な手順を見てきたわけですが、一つ気をつけていただきたいことがあります。それは、根本原因が外部の環境、つまり組織や他人のせいだと決めつけてしまわないようにするということです。必要以上に何でもかんでも自分が悪いと思う必要もないですが、自分が変わることで実は改善できる余地があるにも関わらず、「自分は何も悪くない、全部あの上司や同僚のあの人が悪い」と思い込んでしまっていると、根本原因には辿り着けません。
一見、自分で改善んできる余地がないように感じられることであっても、立ち止まって考えてみて下さい。原因が自分自身の中にあると認識できれば、それを変えるための行動を起こすことが可能になります。
以上、私が長時間労働というQOLへの影響度が大きい課題に対して取り組んできた方法についてお話しました。あなた自身の課題についても、深掘りして根本原因を見つけ、それに対処する方法を見つけることができますように。そして、そんなあなたを周りの人がサポートしてくれますように。
次のステップについては以下の記事にて解説していますのでぜひご参照ください。