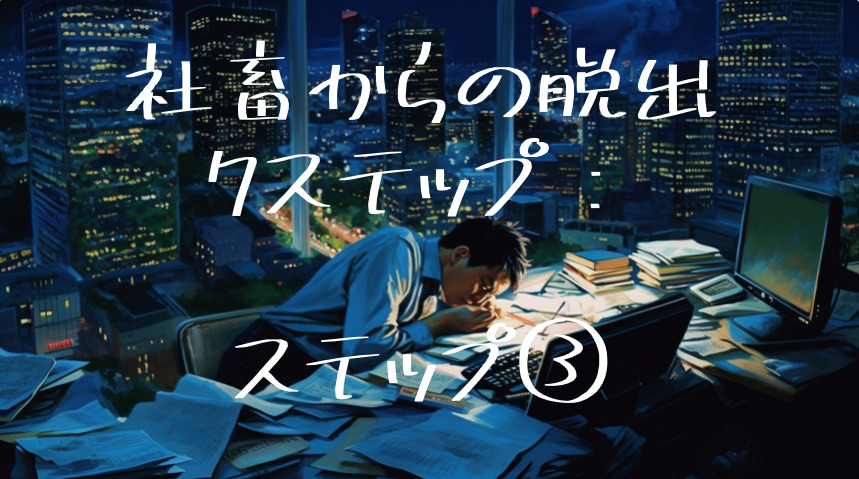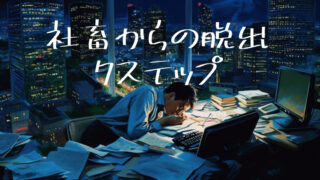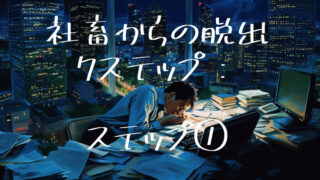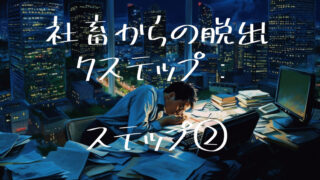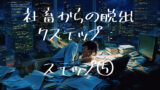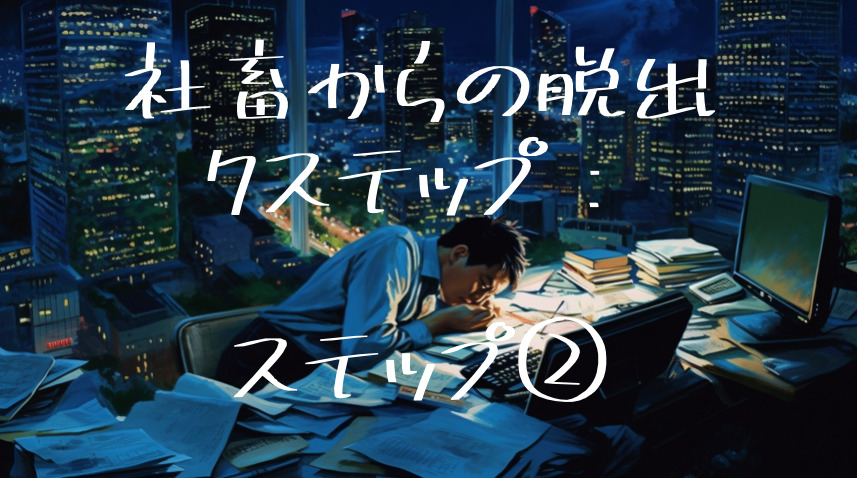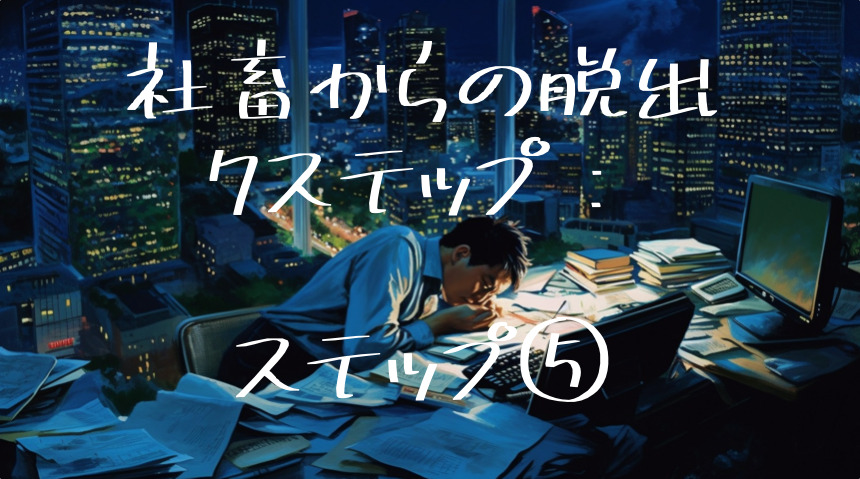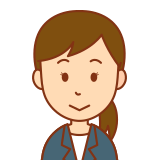
残業多すぎ、朝出勤早くてメイクする時間ない、ランチ食べる時間ない、帰宅が深夜になる、スーパー閉まってて夕食は週5でカップラーメン、睡眠不足で常に頭ぼーっとしてる、趣味のことが全くできない、などなど…もう!どうしたらいいの…
はじめに
毎日残業をしながら「こんな働き方をしたいわけじゃないのに…。」と感じていませんか?実は自分が望んでいる「理想の働き方」と、現実の働き方がかけ離れていて、そのギャップに悩んでいるのではないでしょうか?
そのギャップ、それがまさしく「課題」なのです。つまり、課題とは「あるべき姿」と「現状」の間にあるズレのことなんです。あなたが直面しているストレスや困難、それらすべては「課題」を具現化したものと言えます。
今回は「課題」が沢山ありすぎる場合の優先順位の決め方について掘り下げていきます。フォーカスすべき課題を見つけることが、まずは第一歩。そこから何を改善すべきかを見つけるための道筋が見えてきます。
では、一体まず何から手をつければいいのでしょうか?その答えを見つけるために、今回は具体的な例を交えながら、課題に優先順位をつける実践的な方法について見ていきましょう。
あるべき姿と現状をリストアップすることで課題を可視化する
これより先に進む前に、ぜひこちらの記事を順番にご覧いただき、以下の具体例のように「あるべき姿」と「現状」を表にまとめてみてください。
<具体例:働き方の各トピックについて、あるべき姿と現状を整理した表>
| トピック | あるべき姿 | 現状 |
| 仕事内容 | 自分のスキルを活かせ、意義を感じられる業務に携わりたい。 | ルーチンワークが多く、毎日が単調である。新しいことを学ぶ機会も少ない。 |
| 労働時間 | 1日8時間を基本に、適度な休憩を挟みつつ働きたい。 | 実際には1日10時間以上働いており、休憩時間も十分にとれていない。 |
| 勤務時間帯 | 朝9時から夕方6時までの通常の勤務時間で働きたい。 | 夜遅くまで、時には深夜に及ぶ仕事が多く、ライフスタイルが乱れている。 |
| 休暇日数・休暇制度 | 年間に最低でも週1の休日と長期休暇を確保したい。 | 土日休みがほとんど保証されず、長期休暇もほとんどとれない状況である。 |
| 給与・報酬 | 長時間労働に見合った報酬を得たい。 | 残業代がきちんと出ないなど、労働に対する報酬が不十分である。 |
| 上司に対して望むこと | 労働環境の改善やキャリアアップをサポートしてくれる上司が欲しい。 | 上司は業績の追求にしか興味がなく、私のキャリアや働き方には無関心である。 |
| 組織内の人間関係 | コミュニケーションがスムーズで、働きやすい職場環境を望んでいる。 | 人間関係のストレスが高く、業務に影響が出ている。 |
| 企業文化 | ワークライフバランスを重視し、個々の働き方を尊重する企業文化があるべきだと思っている。 | 業績至上主義の企業文化で、長時間労働が常態化している。 |
| キャリア形成とスキルアップ支援 | 会社からのキャリア形成の支援や研修等の教育制度があるべきだと考えている。 | 社内研修や教育制度がほとんどなく、自己啓発が必須となっている。 |
| 家庭や趣味などの私生活 | 仕事以外の時間も充実させ、ワークライフバランスを保ちたい。 | 長時間労働のせいで、家庭や趣味の時間が極端に少ない。 |
自分の不平不満や気に入らないこと、ストレスになっていることなどがだいたい網羅されていればOKです。
課題の優先順位をつけよう
多くの人が、自分の課題を見つけると一度に全て解決しようとします。しかし、それは現実的なアプローチではありません。私たちは全てを同時に解決する能力はありません。そこで必要になるのが、課題に優先順位をつけることです。
全ての課題が同じ重要度を持っているわけではありません。それぞれの課題が与える影響の大きさ、緊急度、取り組むことで得られる効果などによって、課題の重要度は変わってきます。そのため、課題に優先順位をつけて、最も重要な課題から解決していくことが重要なのです。
課題に優先順位をつけることによって、次に何に取り組むべきかが明確になり、その結果、自分自身の労力と時間を最も効率的に使うことができます。また、最も重要な課題から解決することによって、全体の改善効果も大きくなります。
では、具体的にどうやって課題の影響度を評価し、優先順位をつけるのでしょうか。その方法について見ていきましょう。
まずは、QOL(生活の質)への影響度を評価しよう
さて、課題に優先順位をつけるためには、まず各課題がもたらす影響度を評価することが必要です。影響度とは何かと言うと、それは課題が解決されたときに得られるポジティブな効果や、逆に課題が放置されたときに生じるネガティブな影響の大きさを指します。
例えば、長時間労働が原因で健康を害している場合、この課題が解決されれば健康状態が改善される可能性があります。一方で、この課題が放置された場合、健康状態は悪化し、最終的には仕事ができなくなる可能性すらあります。これは非常に大きな影響度を持つ課題と言えるでしょう。
影響度を評価するには、まず全ての課題をリストアップし、それぞれがどの程度の影響をもたらすかを考えることが必要です。この段階では具体的な数値を出す必要はありません。課題が解決されたときのポジティブな効果と、放置されたときのネガティブな影響を考えるだけで十分です。
この評価は自分だけで行うことも可能ですが、周りの人の意見を聞くことでより客観的な評価ができるでしょう。上司や同僚、友人や家族など、自分の視点だけでなく他人の視点からも考えてみることで、自分では気づかなかった課題の影響度に気づくことができます。
では、以下の具体例を見てみましょう。
<具体例:働き方の各トピックについて、QOLへの影響度を評価した表>
| 課題 | 影響度 | 評価基準 | 評価の理由 |
| 仕事内容 | 3 | 仕事の内容が自己実現や満足感に直結する。 | ルーチンワークが多いと日々のやりがいを感じにくくなるため。 |
| 労働時間 | 5 | 労働時間が長いほど自由な時間が減り、ストレスが増える。 | 過度の労働は肉体的・精神的な健康を蝕むため、QOLに大きな影響を与える。 |
| 勤務時間帯 | 4 | 生活リズムが乱れると健康に影響を及ぼす。 | 夜遅くまで働くと、睡眠時間が減少し、体調管理が難しくなる。 |
| 休暇日数・休暇制度 | 5 | 休暇が取れないと身体的、精神的に休む時間がない。 | 休暇が確保できないとリフレッシュする時間がなく、ストレスが溜まりやすい。 |
| 給与・報酬 | 3 | 報酬が生活水準やモチベーションに影響する。 | 給与が低いと生活が苦しくなり、働くモチベーションも下がる。 |
| 上司に対して望むこと | 2 | 上司との関係性が仕事のやりがいやモチベーションに影響を及ぼす。 | 上司の理解が得られないと、仕事に対するモチベーションや自己実現感が低下する。 |
| 組織内の人間関係 | 4 | 人間関係のストレスは心身の健康を脅かす。 | 悪化した人間関係は、ストレスを増加させ、仕事意欲や自己肯定感に影響を及ぼす。 |
| 企業文化 | 3 | 企業文化が働き方や仕事への意識に影響を及ぼす。 | 企業文化が働き方に大きく影響を与え、それがQOLに影響を及ぼす。 |
| キャリア形成とスキルアップ支援 | 2 | キャリア形成支援が自己成長や職業満足度に寄与する。 | 社内研修や教育制度がほとんどないと、自己成長が制約される。 |
| 家庭や趣味などの私生活 | 5 | ワークライフバランスが保たれないと心身の健康や生活満足度に影響する。 | 家庭や趣味の時間が取れないと、ストレス発散や自己成長の機会が減少する。 |
この例では個々の課題が日々の生活の質にどれだけの影響を及ぼしているかを、1〜5の5段階で評価しています。各評価基準は以下のように定義しました。
- 評価1:この課題は現在の生活の質にほとんど影響を及ぼしていない。問題が解決されても生活の質はほぼ変わらない。
- 評価2:この課題は少ないながらも生活の質に影響を及ぼしている。問題を解決することで一部の生活の質が改善されるかもしれない。
- 評価3:この課題は生活の質に中程度の影響を及ぼしている。問題が解決されれば、生活の質は明らかに改善される。しかし、それでも日々の生活はそれなりに管理できている。
- 評価4:この課題は生活の質に大きな影響を及ぼしている。問題が解決されなければ、生活の質は大幅に低下する可能性がある。この問題が日々の生活にかなりのストレスをもたらしている。
- 評価5:この課題は生活の質に非常に大きな影響を及ぼしている。この問題が解決されなければ、生活の質は極めて低下し、健康や幸福感を大きく損なうことにつながる。この問題は緊急に対処を要する。
これらの評価基準はあくまで一例であり、個々の状況や価値観によって評価しやすい方法で評価してください。最終的に各課題がQOLにどの程度影響を及ぼしているか評価することができればOKです。
影響度が大きいランキング1位〜3位を決めよう
さて、上記例では影響度5のものが3つあります。これら3つの課題(労働時間、休暇日数・休暇制度、家庭や趣味などの私生活)の中から、QOLへの影響度を再評価し、優先順位をつけます。
<具体例:QOL(生活の質)への影響が大きい課題TOP3>
| 課題 | 優先順位 | 評価基準 | 評価の理由 |
| 労働時間 | 1 | 長時間労働がすぐに健康に影響し、さらに他の生活領域にも悪影響を及ぼす。 | 長時間労働は身体と心に負担をかけ、すぐに健康問題を引き起こす可能性がある。また、労働時間が長いと自由時間が減り、家庭生活や趣味などの私生活への影響も大きい。 |
| 休暇日数・休暇制度 | 2 | 適切な休暇が取れないとストレスが溜まり、疲労回復やリフレッシュができない。 | 休暇が十分に取れないと、心身のリカバリータイムが確保できず、健康問題を引き起こす可能性がある。また、趣味や家庭生活など、仕事以外の活動への影響も大きい。 |
| 家庭や趣味などの私生活 | 3 | 私生活の時間が取れないとストレス発散やリラクゼーションができない。 | 自分の時間が確保できないと、ストレス発散の手段がなくなり、精神的な健康に影響を与える。しかし、労働時間や休暇と比べると、直接的な健康影響は少ない。 |
影響度を評価する基準って何だろう?
さて、ここまでお読みいただいていかがでしょうか。すんなり評価できそうですか?できないよーという方のために、この章では課題の影響度を評価する基準について一例をご紹介します。大きく分けて以下の3つの観点から考えると評価しやすいのではないでしょうか。
- パーソナルな影響:課題が自分自身の生活や仕事にどの程度影響を与えるか。例えば、健康問題、ストレスレベル、モチベーション、仕事の成果などが考えられます。
- チームや組織への影響:課題が自分の所属するチームや組織全体にどの程度影響を与えるか。例えば、チームの生産性、業績、モラール、職場の雰囲気などが考えられます。
- 長期的な影響:課題が将来的にどの程度影響を与えるか。例えば、キャリアパス、自己成長、将来の可能性などが考えられます。
以上の3つの観点から各課題を評価し、それぞれの影響度を比較することで優先順位を決めていきます。このとき、一つの観点だけでなく全ての観点を考慮することが重要です。それぞれの観点が重なり合うことで、課題の真の影響度が明らかになります。
こうして影響度を評価することで、どの課題から手をつけるべきか、どの課題に一番時間とエネルギーを投じるべきかが明確になります。それはまさに自分自身の働き方改革の第一歩と言えるでしょう。
おわりに:課題の設定ができたら半分解決したようなものだ!
さて、ここまで来れば課題の設定と優先順位がつき、あとは行動するだけです。ここまでのプロセスを経て課題を見つけ、その影響度を理解することができれば、それはすでに半分は勝利したも同然です。
「なんとなくモヤモヤとした問題を抱えている」という状態から、「これが問題で、これを解決すれば生活が良くなる」という明るい気持ちになっていただけたら幸いです。
ここまで見えてきたら、次に進む一歩が怖くても大丈夫。あなたがこれから進むその道は、あなた自身が選んだ、自分の生活をより良くするための道だからです。
大事なのは、自分で決めた道を進む勇気を持つこと。そして、途中で挫折しそうになったら、この記事を思い出して、もう一度自分の課題とその影響度を見つめ直してみてください。
次のステップについては以下の記事にて解説していますのでぜひご参照ください。